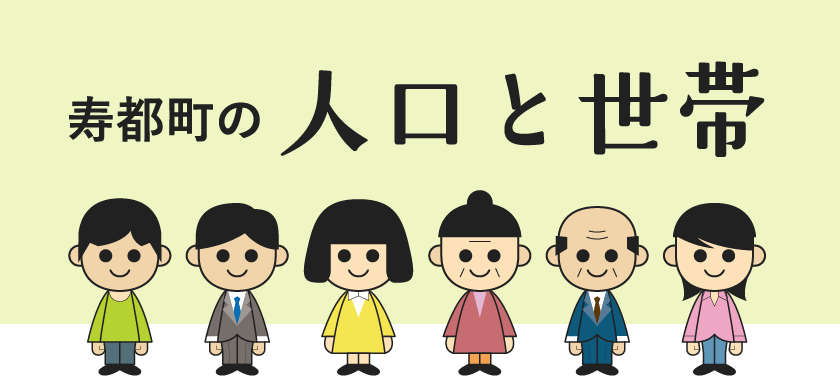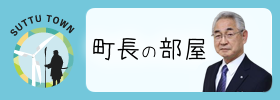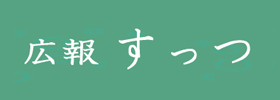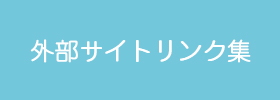くらしの案内
国民健康保険制度について
国民健康保険とは
国民健康保険は、病気やけがの際にいつでも安心して診療が受けられるように、加入者の皆さんが日ごろから所得に応じて保険料を出し合い、お医者さんにかかるときの医療費にあてようという「相互扶助」の医療保険制度です。
加入の手続きについて
寿都町内に引越して来られた下記の加入対象者に該当する方、または職場の医療保険などを脱退された方は、国民健康保険への加入手続きが必要になります。
対象者
町内にお住まいの方で下記(1)~(3)以外の全ての方が国民健康保険の加入対象者となります。
(1) 職場の健康保険・船員保険・共済組合などの加入者とその被扶養者
(2) 国民健康保険組合加入者
(3) 生活保護受給者
※また、外国籍の方で資格が特定活動の方(旅行者・一時滞在者・在留期間が切れた方を除く)も加入対象となります。
届 出
必要なものを準備のうえ、14日以内に届出をしてください。
届出が遅れると、保険料をさかのぼって納めていただきます。
また、その間の医療費は原則として全額自己負担となります。
必要なもの
- 引っ越してきたとき・・・転出証明書
- 職場の健康保険などをやめたとき・・・社保資格喪失証明書
- 生活保護を受けなくなったとき・・・保護廃止通知書
- 子どもが生まれたとき・・・母子手帳
脱退の手続について
国民健康保険の加入者とその被扶養者の方が、寿都町外へ引越するとき、職場の健康保険などに加入したとき、生活保護を受けるとき、死亡したときには、脱退の手続きが必要です。
脱退するときは必ず保険証を返却してください。
施設入所等や修学のために転出するとき
寿都町の国民健康保険に加入されている方が、町外へ転出されると加入資格が無くなりますが、下記対象者に該当する場合は資格が特別に継続します。
届出が必要ですのでご注意ください。
対象者
(1) 特別養護老人ホームなどへ入所するとき
(2) 修学のため、他の市町村に住居を定めるとき
(3) 児童福祉施設などに入所するとき
届 出
住民票の転出届けの手続が必要です。
町民課 住民係の窓口で手続をしてください。
必要なもの
保険証と下記のいずれか1点
・施設入所の案内資料(特別養護老人ホーム)
・在学証明書(修学)
・在園証明書(児童福祉施設)
保険診療と一部負担金(高額療養費)について
病院等で国民健康保険証を提出すると、かかった医療費の一部負担金と、入院時の食事代の一部を加入者が負担し、残りの医療費を国民健康保険が負担します。
医療費の自己負担割合
(1) 義務教育就学前 → 2割
(2) 義務教育就学から70歳未満 → 3割
(3) 70歳以上 → 2割(誕生日が昭和19年4月1日までの方→特別措置により1割)
(4) 70歳以上75歳未満の現役並みの所得の方 → 3割
次の場合は、世帯主の請求によって、支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。
ただし、場合によっては、払い戻しができないこともありますので、ご注意ください。
(1) 急病などで、緊急またはやむを得ない理由で国民健康保険証を提出できずに医者にかかったとき。
(2) 医師が必要と認めたマッサージ・はり・きゅうの施術をうけたとき。
(3) 医師が必要と認めたコルセットなどをつくったとき。
保険診療ができないもの
(1) 健康診断・美容のための処置、正常な妊娠や分娩、歯並び矯正、予防注射など病気とになされないもの。
(2) 犯罪、麻薬中毒や自分の故意によるケガや病気
(3) 仕事中や通勤途中上のケガや病気(労災に該当する場合)
高額療養費
70歳未満の方はこんなとき高額療養費が支給されます。
支払った自己負担額が高額となったときは、高額療養費が支給されます。高額療養費は月単位で、医療機関ごと、入院・外来・調剤・歯科別に、それぞれの自己負担額が21,000円以上のものを合計した額が、次の表の自己負担限度額を超える場合に支給されます。
70歳未満の人と、70歳以上の人では、自己負担限度額が異なります。
高額療養費(70歳未満)
| 所得要件 | 自己負担限度額 | 認定証 | |
|---|---|---|---|
| ア※3 | 旧ただし書所得(※1) 901万円超の方 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数回該当(※2):140,100円) |
限度額適用認定証 |
| イ | 旧ただし書所得(※1) 600万円超~901万円以下の方 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (多数回該当(※2):93,000円) |
|
| ウ | 旧ただし書所得(※1) 210万円超~600万円以下の方 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (多数回該当(※2):44,400円) |
|
| エ | 旧ただし書所得(※1) 210万円以下の方 |
57,600円 (多数回該当(※2):44,400円) |
|
| オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 (多数回該当(※2):26,400円) |
限度額適用・標準負担額減額認定証 |
※1 「旧ただし書所得」とは、総所得金額から基礎控除額(43万円)を差し引いた所得額をいいます。
※2 「多数回該当」とは、高額療養費の該当が過去12か月以内に4回以上になったときの4回目からの限度額をいいます。
※3 所得要件の「ア」~「オ」は「認定証」に記載される区分を示しています。高額な医療を受ける場合、入院などにより医療費の負担が高額になる場合には、あらかじめ町に申請して「認定証」(限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受け、医療機関などの窓口に提示することで、同一の医療機関での同一月の自己負担額を高額療養費の限度額までとすることができます。
注:入院の際は、役場町民課医療係の窓口で申請が必要です。
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)
| 区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 | 認定証 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
||||
| 現役並み所得者 ☆1 | Ⅲ | 課税所得690万円以上 | 252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% 多数回該当(140,100円) |
不要 | |
| Ⅱ | 課税所得380万円以上 690万円未満 |
167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% 多数回該当(93,000円) |
限度額適用認定証 | ||
| Ⅰ | 課税所得145万円以上 380万円未満 |
80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% 多数回該当(44,400円) |
|||
| 一般 | 課税所得145万円未満 | 18,000円 年度限度額(144,000円) |
57,600円 多数回該当(44,400円) |
不要 | |
| 低所得者 Ⅱ ☆2 | 住民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 | 限度額適用・標準負担額減額認定証 | |
| 低所得者 Ⅰ ☆3 | 住民税非課税 (所得が一定以上) |
8,000円 | 15,000円 | ||
○申請に必要なもの
・国民健康保険被保険者証
・印鑑
・医療機関が発行した領収書
・世帯主の預金口座番号がわかるもの
国民健康保険第三者行為(交通事故等)による届出について
第三者行為とは
第三者(自分以外の人)が原因として治療を受けることになった場合を指します。
主な例として、交通事故がこれにあたります。
※自損事故は第三者行為になりませんが、給付を受けるためには届出が必要となっています。
なお、飲酒運転や、無免許運転による負傷などの悪質な法令違反の場合は、給付違反にはなりません。
医療費は加害者(相手)が負担
交通事故などにより病院にかかった場合の治療費は、本来加害者(第三者)が負担すべきものですが、国保を使って治療をうけることができます。
このような場合の治療費は国保が一旦立替えをして、後日、加害者にその立替え分を請求することになります。
ただし、加害者側への請求を行う為には被害者側からの届出が必要となりますので、国保を使うときは必ず町民課医療係へ届け出て下さい。
申請に必要なもの
・国民健康保険被保険者証
・印鑑
・事故証明書等(様式等は町民課医療係まで連絡願います)
その他の給付について
出産育児一時金制度について
国民健康保険に加入している人が出産したとき、申請をすると48万8千円(産科医療補償制度に加入の分娩機関で出産の場合は50万円)が支給されます。
(死産や流産でも妊娠85日以上であれば支給されます。)
※ 出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、病院などに直接支払うことができます。
○必要なもの
・医師証明書(申請書に記載)
【担当部署】役場 町民課 医療係 TEL:0136-62-2523(内線33)
葬祭費の支給について
国民健康保険に加入している人が死亡したときは、葬儀を行った人に3万円が支給されます。
○申請に必要なもの
・印鑑
・口座情報
・会葬礼状
【担当部署】役場 町民課 医療係 TEL:0136-62-2523(内線33)
国民健康保険税について
納税義務者について
被保険者である世帯主を納税義務者をして課税します。ただし、被保険者でない世帯主であっても、その世帯内に被保険者がいる場合は、その世帯主に課税されます。
賦課期間および月賦賦課について
賦課期間は、その年度の属する4月1日現在です。
賦課期間後に納税義務が発生または消滅並びに世帯内の被保険者の異動(出生、死亡、転入、転出、他保険加入、他保険離脱等)があった場合は、月賦賦課となります。
税率および課税額について
国民健康保険税は世帯内の国民健康保険に加入している人それぞれの所得割・均等割を計算し、その世帯で合算し、平等割を加えた額が課税されます。
*所得割とは・・・前年の所得に対する額
*均等割とは・・・被保険者数に対する額
*平等割とは・・・1世帯あたりに対する額
国民健康保険税は国民健康保険に要する費用の(医療分)に充てるための課税額、介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用(介護分)に充てるための課税額、平成20年度からスタートした「後期高齢者医療制度」に要する支援金(後期高齢者分)の合算額です。
ただし、医療分の課税限度額は66万円、介護分の課税限度額は17万円、後期高齢者分の課税限度額は26万円となっています。
また、介護分は国民健康保険の被保険者のうち40歳以上65歳未満の被保険者につき算定されます。
国民健康保険の税率
| 賦課割合 | 課税の基礎 | 医療分 | 介護納付金分 | 後期高齢者支援分 |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 課税所得金額 | 7.8% | 1.9% | 2.6% |
| 均等割 | 被保険者一人につき | 25,000円 | 7,800円 | 8,000円 |
| 平等割 | 一世帯につき | 22,000円 | 5,800円 | 8,000円 |
保険税の納期
国民健康保険税の納期については、6月~12月それぞれの月末日(祝祭日の場合は翌日)の7期となっており、12月以降は随期とし、翌年3月31日までとなっています。
※平成20年10月から、65歳以上の方のみで構成する世帯については、税金が年金より天引きされることとなりました。
保険税の軽減
① 国民健康保険税では、前年の総所得が一定の基準以下の場合、均等割・平均割の軽減を行っています。
◇ 43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数-1)×10万円
7割軽減
◇ 43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数-1)×10万円+30.5万円×(被保険者数)
5割軽減
◇ 43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数-1)×10万円+56万円×(被保険者数)
2割軽減
② 非自発的失業(離職)により国民健康保険へ加入する方の国民健康保険税について、失業(離職)から一定の期間、前年の給与所得を30/100として算定し賦課することにより、国民健康保険税を軽減します。ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得は通常の額を用います。
・対象者
平成21年3月31日以降に失業(離職)された方で、雇用保険を受給している特定受給資格者又は特定理由離職者(公共職業安定所が発行する「雇用保険受給資格者証」で確認します。)
| コード番号 | 離職理由 |
|---|---|
| 11 | 解雇 |
| 12 | 天災等の理由により事業継続が不可能となったことによる解雇 |
| 21 | 雇止め(雇用期間3年以上 雇止め通知あり) |
| 22 | 雇止め(雇用期間3年以上 更新明示あり) |
| 31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
| 32 | 事業所移転に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
| コード番号 | 離職理由 |
|---|---|
| 23 | 期間満了(雇用期間3年未満 更新明示なし) |
| 33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
| 34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
【担当部署】役場 総務財政課 税務係 TEL:0136-62-5212(内線22・24)
おくすりについて
バイオシミラーについて
バイオシミラー(バイオ後続品)とは
「バイオ医薬品」は、バイオテクノロジーを応用して生産されたタンパク質を有効成分とする医薬品で、今までは治療が難しかった病気にも効果が期待されています。
「バイオシミラー(バイオ後続品)」は、この「バイオ医薬品」の特許が切れた後に販売される医薬品で、「バイオ医薬品」と同等・同質の品質、安全性や有効性を有しています。開発費が低く抑えられているため、「バイオ医薬品」よりも低価格となっております。
「バイオシミラー(バイオ後続品)」の処方を希望される場合は、かかりつけの医師や薬剤師にご相談ください。
リフィル処方箋について
リフィル処方箋とは
長期にわたり変更なく飲み続けているお薬について、かかりつけの医師の処方により、医師及び薬剤師の適切な連携のもと、一定期間内に同じ処方箋を繰り返し利用することができる仕組みです。
症状が安定し通院をしばらく控えても問題ないとかかりつけの医師が判断した場合に対象となりますので、詳しいことはかかりつけの医師までご相談ください。